 観劇レポート
観劇レポート 海老蔵歌舞伎(明治座)の演目、あらすじ、感想、評価は?
海老蔵歌舞伎を観劇しました。メディアでも、34年ぶりの親子共演が話題になっていましたね。その公演の内容や感想などをお伝えします。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 観劇レポート
観劇レポート  歌舞伎演目
歌舞伎演目  歌舞伎演目
歌舞伎演目  歌舞伎演目
歌舞伎演目  観劇レポート
観劇レポート  歌舞伎演目
歌舞伎演目 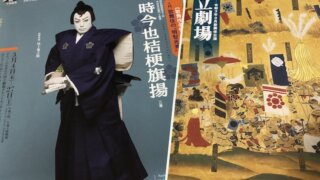 歌舞伎演目
歌舞伎演目  歌舞伎演目
歌舞伎演目 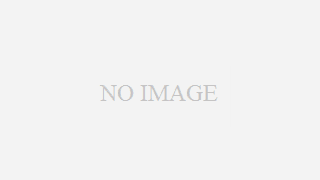 メディア出演
メディア出演 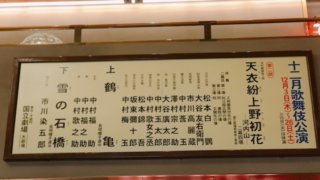 観劇レポート
観劇レポート  歌舞伎演目
歌舞伎演目  歌舞伎演目
歌舞伎演目